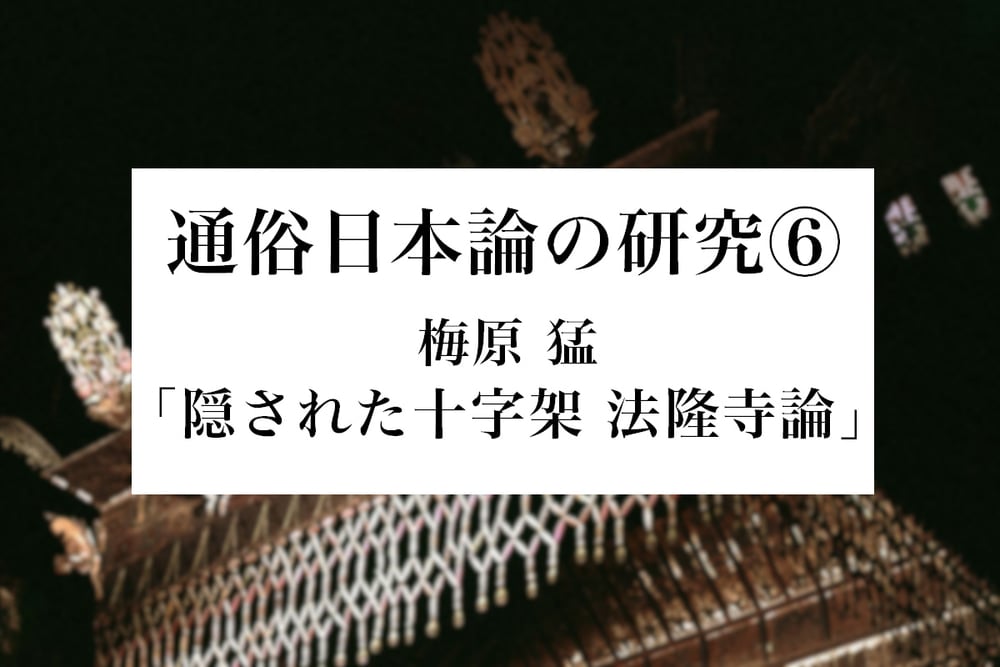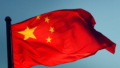法隆寺金堂
法隆寺HPより
哲学者梅原猛氏には数多くの著作があるが、それらの中でも読書界に最も大きな衝撃を与えた代表作は『隠された十字架 法隆寺論』(新潮社、1972年)であろう。その骨子を知らない人はいないだろうが、念のため説明しておくと、同書で梅原氏が提起した仮説は、法隆寺が聖徳太子の怨霊を慰める鎮魂の寺であるというものである。
これは非常に斬新な仮説であるが、同書が大ヒットした理由は、仮説の中味よりも、むしろ叙述の形式だったと思われる。同書の冒頭で梅原氏は「法隆寺七つの謎」を提示する。
曰く、
- 『日本書紀』が法隆寺の全焼について記しながら、法隆寺の建造および再建について一言も語らないのは何故か
- 『法隆寺資材帳』が法隆寺の焼失と再建について記さなかったのは何故か
- 法隆寺の中門の真ん中に柱があるのは何故か
- 法隆寺の金堂に薬師・釈迦・阿弥陀の三体の本尊があるのは何故か
- 『資材帳』に記載された塔の高さが現実の塔より1.5倍も高いのは何故か
- 夢殿の救世観音が厳重に秘仏にされねばならなかったのは何故か
- 法隆寺の最も重要な祭りである聖霊会で、舎利と太子七歳像が一緒に供養されるのは何故か
の七つである。
こうして自ら提示した謎を、梅原氏は鮮やかに解いてみせる。その内容をここで明かしてしまうことは、これから同書を読む方の興を削ぐことになるので控えるが、圧倒的な情報量を誇る同書に挑んだ多数の読者が消化不良を起こさず、かえって喝采を送ったのは、このミステリ仕立ての構成によるところが大きいだろう。この手法の最も忠実な模倣者が、『逆説の日本史』で知られる推理小説家の井沢元彦氏であることは言うまでもない。
しかしながら、謎解きに傾斜する梅原氏の研究姿勢は、当然のことながらアカデミズムの世界から白眼視された。日本古代史の大家である坂本太郎は「法隆寺怨霊寺説について」(『日本歴史』300号、1973年)で、「この本の面白さは、その推理の面白さである。その推理が動かし難い歴史事実にもとづいているかどうか。その点になると、私は疑問を抱く」と批判する。
坂本は梅原古代学の根幹とも言える「稗田阿礼=藤原不比等」説(『古事記』・『日本書紀』の制作主体を不比等とみなす説)を完膚なきまでに論破しているが、その紹介は煩雑になるので本稿では省く。
坂本の批判は、聖徳太子の怨霊を恐れた藤原氏が全焼した法隆寺を再建し、以後も莫大な寄付を続けたという同書の中心的な主張にも及んでいる。仮に聖徳太子の怨霊なるものが人々に恐れられたという事実があれば、何か当時の文献にその片鱗を残しているはずであるのに、たくさん書かれた太子伝に少しもそういう徴証は見えない。太子の死霊が後人を悩まし、天下に害を与えたなどと書かれた史料は、一つもない。
藤原不比等の四人の子ども(藤原四子)が天然痘で相次いで亡くなった時でさえ、かつて彼らが滅ぼした長屋王の怨霊を恐れて長屋王のために特別の像を造ったとか、寺を建てたとかいう事実はないのに、百年余りも前の聖徳太子の怨霊を藤原氏が恐れるはずがない。
梅原氏は、藤原不比等が聖徳太子の霊を慰めるために『日本書紀』において太子を神格化したと主張するが、その太子の怨霊を鎮めるための寺であるはずの法隆寺についての記事が乏しいのは何故か。火事にあったことを書くくらいならば、精根こめて再建に努めたことを書く方が、太子の霊を慰めることになるのではあるまいか、などなど、挙げれば切りがない。
梅原氏の怨霊史観は今なお根強いファンを持っているが、歴史学界から見れば、とっくの昔に否定された奇説でしかないのである。
ただ本稿の目的は、半世紀前に発表された著作の欠陥を今さらあげつらうことにあるのではない。この時期に梅原氏が怨霊に強い関心を持った理由、世間が梅原氏の怨霊史観に強く惹きつけられた理由こそを考えるべきだろう。
梅原氏が同書の原型となる論考を季刊誌『すばる』で連載していた1970年末~1971年は、新左翼の思想がまだ輝きを残していた時代であった。1968年に頂点を迎えた西側先進諸国の学生反乱が掲げた理念の一つは、近代合理主義批判である。梅原氏がポストモダン論に共鳴していたとは思えないが、人間の非合理性に注目する氏の怨霊史観が時代の雰囲気に影響されて生まれた可能性はあろう。
中国の文化大革命の現実がまだ伝わっていなかった頃、日本の左派知識人は、物質第一主義ではなく精神性を重視していると文革を称賛した。したがって、合理主義や物質第一主義を批判する考え方はマルクス主義の内部から登場したものである。ところが梅原氏は、こうした思想をマルクス主義批判に利用した。氏は『神々の流竄』で次のように語っている。
私がいいたいのは、戦後日本の歴史学者のとった物質万能の考え方では、とうてい、歴史の真実は見えがたいということである。なぜなら、人間は、卑俗な唯物論者が信じるよりはるかに精神的存在であるからである。物質的存在であると共に精神的存在である人間を研究するのに、精神の研究を度外視して、到底、真実の解明は不可能なのである。
梅原氏は『隠された十字架』でも「もとより、専門家の歴史家でも、仏像学者でも、建築学者でもない私は、認識の過程で若干の誤りを犯しているかもしれない」とアマチュア性を標榜しつつ、専門家の視野の狭さを厳しく批判する。氏の意図はどうあれ、こうした〝専門家を斬る〟語り口が商業的な成功につながった側面は否めない。
それでも梅原氏には専門家への敬意の念があったが、そのエピゴーネンは学界の最新研究に学ぶことなく学者を「専門バカ」と罵り、時代潮流の変化を意識することもなく十年一日のごとく同じ主張を繰り返す。通俗日本論も行き着くところまで行ってしまったと感じる。
【関連記事】
・通俗日本論の研究①:堺屋太一『峠から日本が見える』
・通俗日本論の研究②:渡部昇一『日本史から見た日本人 古代篇』
・通俗日本論の研究③:渡部昇一『日本史から見た日本人 鎌倉篇』
・通俗日本論の研究④:渡部昇一『日本史から見た日本人 昭和篇』
・通俗日本論の研究⑤:梅原猛『神々の流竄』