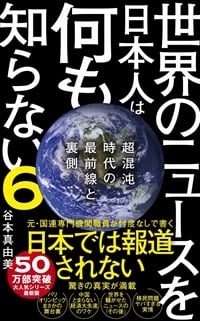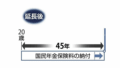海外に住んでいる日本人の中には外国に駐在員として数年間だけ住むという方が結構いますね。
そういった人々の投稿を読んでいてとても気になっている点が、日本の駐在員は子供を現地の学校に入れて教育をしている例が少なくないということです。
現地に日本の学校がなかったり通信教育の手段がないところの場合は仕方ないのかもしれませんが、それでもイギリスや欧州の他の国の駐在員になる人々の感覚とはずいぶん違うので驚かされることがあります。
イギリスや欧州の他の国カナダやアメリカの人達も仕事の都合で海外に駐在したり、自ら外国に住むという人たちが少なくありません。
私がかつて勤めていた国連専門機関や投資銀行も同じです。キャリアアップのためや会社の命令で海外に住まざるを得ないので子供がいると教育をどうするかということが大変な頭痛の種になります。
ところがイギリスや欧州カナダやアメリカの人々の場合は子供を連れて駐在する場合でも実は現地の学校に子供を入れることはほとんどありません。
現地にずっと住むとか配偶者が現地の人である場合は現地の学校に通う例もあります。でもそれはどちらかというとかなり例外です。

monzenmachi/iStock
多くの場合は自分の出身国の系列のインターナショナルスクールに入れます。その場合学費は職場が負担することが少なくありません。もしくは自分の国にある宿舎付きの私立の学校に子供を入学させ夫婦で他の国に赴任します。国連専門機関の人々もそういうパターンが少なくありません。
子供とは長期休暇の間などに会いに行きます。休暇も日本より長いのでそういったことが可能になります。また海外に赴任するような人々が勤務する組織というのはお金があるので福利厚生の一部として学校の費用や子供が親元に移動する費用なども負担してくれたりします。
したがって子供を言葉もわからず文化も全く異なる現地校に通わせるという選択肢がほとんどないのです。
言葉がわからなければ子供は他の生徒と人間関係を作れませんし、そもそも勉強がほぼ不可能です。子供の中には何とか現地の言葉を勉強して勉強についていけるようになる子供もいますが、しかしその負担は大変なものです、母語でない言葉で学ぶことは大人であっても大変なことです。
しかも外国語で学ぶことに時間を費やさなければならないので自分の母語の発達も遅れます。
特に小学校中学年から中学生ぐらいだと概念や理論的なことを学び始める時期ですから、その時期に母国語での学びや算数の学習で深い部分まで理解ができないと成人してから深い思考が行えないといった弊害が出てきます。
実はこれは旧植民地の国の人々の間で問題になっていることです。学校で使う言語は自分の母語ではない英語やフランス語なので概念が理解できなかったり、言語的に深みのある表現をすることができないのです。
ですからイギリスや欧州、カナダ、アメリカなどの人々に、日本の駐在員は子供を言葉がわからなくても現地の学校に入れて週末に補習校に通わせているのだということを伝えると大変驚く人が多いのです。
彼らは子供の心理的な負担や発達への影響をかなり気にするからです。
私も独身の頃は親の仕事の都合で海外に駐在になっても現地校に行けば子供ならすぐに言葉を覚えるだろうし、勉強にもついていけるだろうという風に思っていました。
しかし私の大学や大学院の同級生には元帰国子女の人々がいましたが、親の仕事の都合で僻地や地方に住んでいた人々は現地校に通っていたので言葉がわからなかったり友達ができなかったりして大変な苦労をしたということを聞き、考え方が変わりました。
さらに自分が実際に子供を持って多言語環境で教育をし、その他にも様々な国の子供を目にしてきて、それは子供にとって大変負担の重いことだということを実感したのです。
最近は大学の帰国子女入試枠を批判する人もいますが、しかしそもそもそういう枠を作らざるを得なかった根本的な理由は、日本の企業というのが海外で駐在する人々に対して十分な福利厚生を提供しないので子供たちが現地校に行かざる得ない状況に置かれることもあり、その救済措置としてできたものだということは理解するべきでしょう。
ちなみにイギリスの大学は帰国子女枠というものがありません。これは親が海外に駐在してもイギリスやアメリカの標準で教育を受けさせるからです。ですから彼らは母国で受験する生徒と全く同じ試験を受けて入学します。
【関連記事】
- 移民の激増でコミケが日本から消滅する未来
- 日本の女子中高生の制服が生命の危機に直結する未来
- 外国人大家による無理のある家賃値上げは規制すべき
- 不法移民による暴動を「単なる反政府デモ」と伝える日本のマスコミの欺瞞
- 帰国子女の苦しみを理解していない人が多い