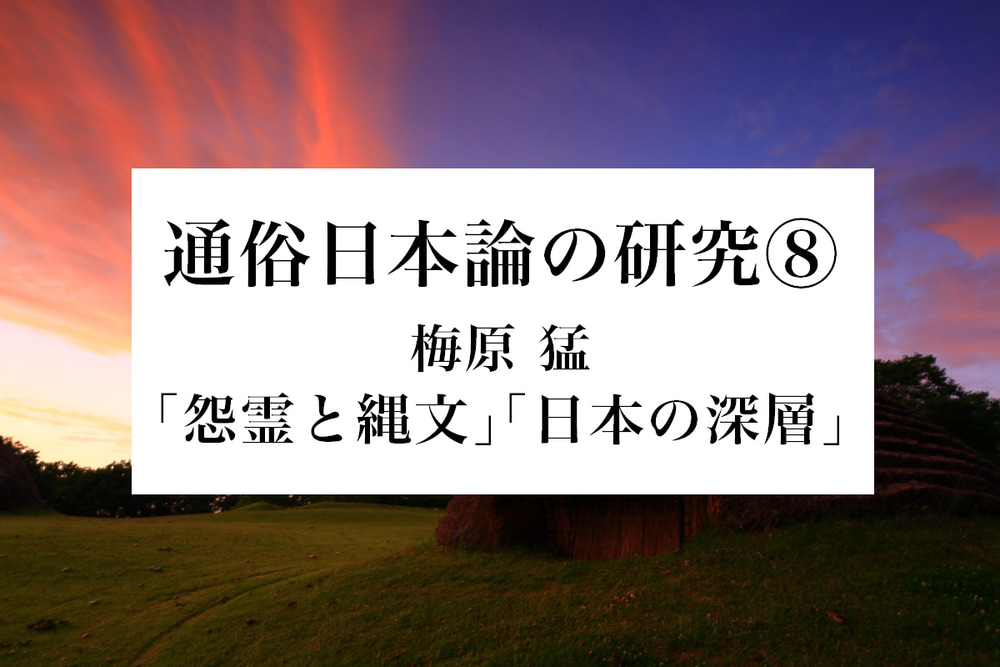哲学者梅原猛氏の「梅原日本学」には2本の大きな柱がある。1つはこれまでの連載で紹介してきた怨霊史観であり、もう1つは縄文文化への独自の考察である。
梅原氏は日本文化の淵源にはエコロジカルな縄文文化があると主張し、自然と共生した縄文の思想によって、自然の征服という欲望に取りつかれた近代を乗り越えようとした。そうした発想の萌芽は、『怨霊と縄文』(朝日出版社、1979年)に見出すことができる。

nattya3714/iStock
『神々の流竄』から始まった梅原氏の古代史探究は、6世紀後半の「聖徳太子論」までさかのぼったが、その時代は中国の思想の影響を受けて開明化された時代であり、「それ以前の日本についてはさっぱりわからない」。「もっと古い日本」、いわば外国文化の影響を受ける以前の“原日本”を追い求めて、梅原氏は縄文文化に着目する。
むろん、日本文化の起源としての縄文文化に注目したのは梅原氏が最初ではない。有名なところでは、哲学者の谷川徹三は「仏教と仏教芸術以前に、日本がまだ歴史時代にはいらぬ遠い昔からすでに日本にあった原始土器」、つまり縄文土器に示されている美の形が「後の日本の造形芸術の発展の諸相の中にも見てとれる」と主張し、狩猟生活の中から生まれた動的・装飾的・有機的で複雑怪奇な美の形を「縄文的原型」と呼び、農耕生活の中から生まれた静的・機能的・無機的で簡素優美な美の形である「弥生的原型」と対置した。
そして谷川は、この2つを日本の美の原型と捉え、「弥生的系譜が日本の美の正系である」としつつ、桃山の障壁画や茶陶、日光東照宮、葛飾北斎などに見られる「縄文的系譜を軽視すべきでない」と論じている(「日本の美の系譜について―縄文的原型と弥生的原型」『世界』286、1969年)。
しかし梅原氏の縄文論のユニークなところは、単に美術の問題ではなく、思想として捉えた点、そして「縄文の思想を解く鍵」としてアイヌ文化に目をつけた点にある。
梅原氏は、前掲書で「原日本人がアイヌと同じか、それに似た狩猟民族であり、縄文土器を使っていた」「そこへ朝鮮半島から弥生系民族が入ってきて、狩猟世界が農耕中心の世界に代わる。当然侵略者と土着民の混血が起こる。それが日本人となる。いっぽうあくまで反抗して東北の方へ逃げていったのが蝦夷である」という仮説を立てた。
さらに梅原氏は『日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る』(佼成出版社、1983年)では「古い日本の文化、いってみれば日本の深層を知るには、縄文文化を知らねばならない」「縄文時代の文化が日本の基本文化になっている」という確信の下、さらに思索を深めていく。
もちろん「文献時代を遠く遡って特に縄文時代となれば、その言葉もわからず、その宗教は見当がつかない。ただの考古学的な遺品だけでは、とても縄文時代の文化の本質を知ることはできない」。けれども「アイヌは最近まで狩猟採集生活を続けていた。とすれば、彼らは縄文人と同じ生活形態を最近まで保存していたのではないか。日本列島の中で狩猟採集生活を続けていたアイヌは、縄文の遺民であるとしか考えられないのではないか」と推測し、アイヌ文化の研究から縄文文化に接近するという方法論を提示する。
さて、梅原氏に代表されるような縄文=基層(深層)文化論に対しては考古学者などから様々な批判が行われ、アカデミズムの世界では「俗流文化論」と位置付けられている(坂野徹『縄文人と弥生人 「日本人の起源」論争』中公新書、2022年)。ただし、本稿ではその問題には立ち入らず、梅原氏が縄文文化とアイヌ文化を結びつける着想をどこから得たのか、少し考えてみたい。
考古学者の山田康弘氏が指摘するように、戦前の歴史教育においては、石器時代の東日本には「日本人種」ではなく「蝦夷人種」(アイヌ)が住んでいた、と教えられた(「梅原と縄文、そしてアイヌ」『ユリイカ』2019年4月臨時増刊号、青土社)。
1925年生まれの梅原氏が、戦前の教育の影響を強く受けていたであろうことは想像に難くない。だが梅原氏は、アイヌと古代日本人という「二つの民族はひとつの元から生じているのではないか。その言語も、その文化も、同じ起源をもつのではないか」と考えており(『日本の深層』)、この点では戦前のアイヌ蔑視的な歴史観と一線を画している。
もう一つ可能性として想定できるのは、岡本太郎の影響だろう。縄文土器の美をいち早く発見し、その魅力を啓蒙普及したのが芸術家の岡本太郎であったことは良く知られている(「四次元との対話-縄文土器論」『みずゑ』1952年2月号)。梅原氏も著作で岡本太郎の功績に言及しており、縄文文化について対談を行ったこともある(梅原猛・岡本太郎・小松左京「忘れられた縄文の文化」、1974年)。
だが岡本太郎は、縄文土器や土偶の芸術性を評価するに留まらず、縄文文化とアイヌ文化の親和性についても語っている。太郎は1957年に岩手を旅した際、特に2つのものに感銘を受けた。1つは、中尊寺の讃衡蔵で見つけた鹿角の護り刀の飾りであり、もう1つは、花巻で見た鹿踊りである。
前者について太郎は次のように評する。「激しいエゾ紋様だ。アイヌ的であり、またまさに縄文文化の気配でもある」。後者についても、「鹿踊りについては、私ははじめから、かつての縄文文化人が鹿の肉を常食にしていた時代の呪術的儀礼からの伝統だとにらんでいた。ちょうどアイヌの熊祭りと同じように」と語っている(『日本再発見 芸術風土記』新潮社、1958年)。
ただし「民族独自の明朗で逞しい美観、民衆のエネルギー」に注目した岡本太郎と異なり、梅原氏は縄文文化・アイヌ文化を近代批判に用いている。そこには1970年代という時代性が刻印されている。
それはさておき、「蝦夷の子孫であることが、蝦夷の後裔であることが、なぜわるいのであろう。アイヌと同血であり、同文化であるということを、なぜ恥としなくてはならないのか」(『日本の深層』)という梅原氏の訴えは、当時としては先進的な考えだったと言える。
しかしながら、現在では、アイヌは「日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族」と定義されている(内閣官房アイヌ総合政策室)。アイヌ文化を縄文文化と結びつけ、日本文化の基盤とみなすことは、ことによると「文化盗用」と批判されかねない。この点でも梅原説、そして同説を起点とする昨今の「縄文ブーム」を相対化していく姿勢が求められよう。
【関連記事】
・通俗日本論の研究①:堺屋太一『峠から日本が見える』
・通俗日本論の研究②:渡部昇一『日本史から見た日本人 古代篇』
・通俗日本論の研究③:渡部昇一『日本史から見た日本人 鎌倉篇』
・通俗日本論の研究④:渡部昇一『日本史から見た日本人 昭和篇』
・通俗日本論の研究⑤:梅原猛『神々の流竄』
・通俗日本論の研究⑥:梅原猛『隠された十字架 法隆寺論』
・通俗日本論の研究⑦:梅原猛『水底の歌 柿本人麿論』