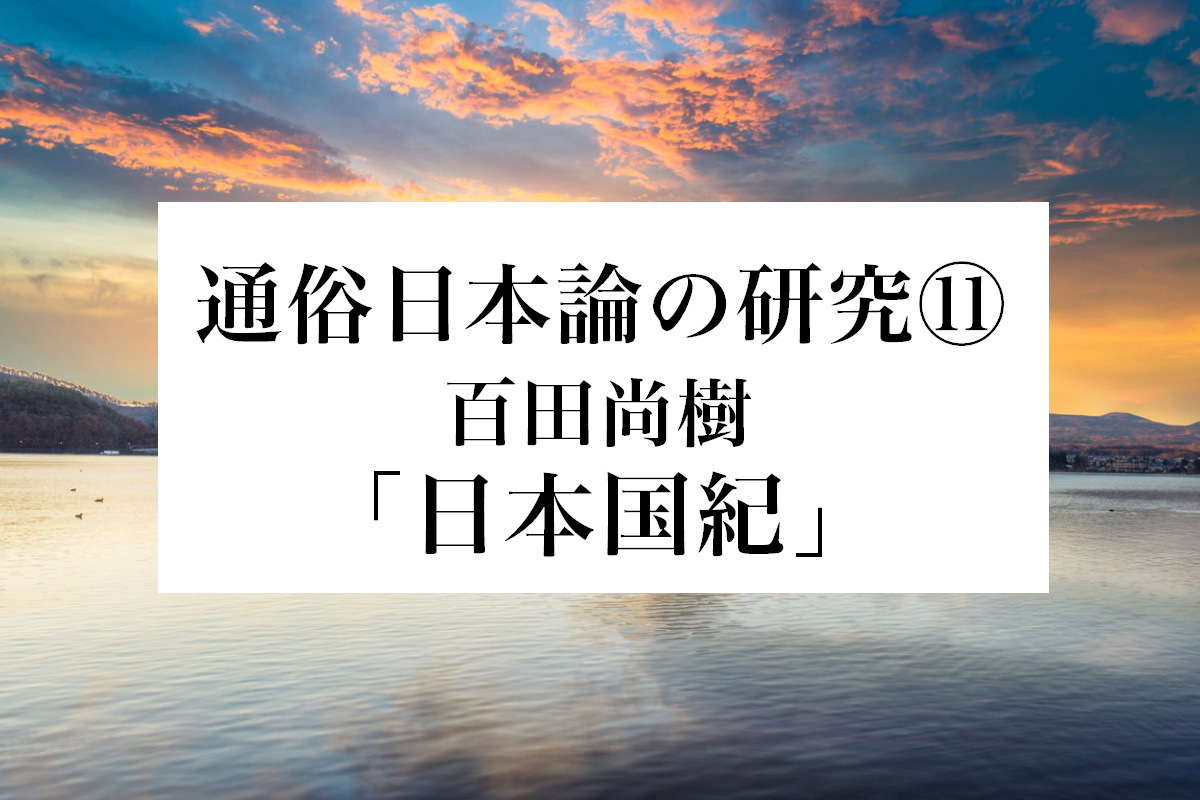primeimages/iStock
近年の日本史関係本での最大のヒット作が百田尚樹氏の『日本国紀』(幻冬舎、2018年)であることは、周知の事実であろう。一方で同書は、事実誤認や誤解を招く記述、俗説の採用などの問題点が刊行当初から指摘された。単行本増刷の際や2021年に文庫化した際に修正された箇所もあるが、それでも問題のある記述が多数残っている。
「日本国紀」の悲しみ 単行本で修正繰り返したが…文庫版も誤り続々

同書単行本の問題点については以前、下記のインタビュー記事でかなり詳しく論じたが、今回は文庫版の問題点を指摘しておきたい。

意外にも百田尚樹氏は、単行本刊行以降に寄せられた批判を無視することなく、事細かく対応している。文庫版では、批判を受けて多くの箇所を修正している。ただ、単行本での主張・記述に未練があるようで、最小限の修正で切り抜けようとする傾向が見られる。この傾向は近現代史の記述で顕著である。
いくつか例を挙げよう。『日本国紀』単行本では「「南京大虐殺」はなかった」と断言していたが、文庫版では「組織的および計画的な住民虐殺という意味での「南京大虐殺」はなかった」と主張を後退させている。
ナチスのホロコーストのような住民虐殺そのものを目的とした行為、ジェノサイドはなかったという趣旨と解されるが、現地の日本軍による略奪・性暴力・虐殺行為などの広範な存在を(消極的に)認めたとも言える。その点では、一見すると、いわゆる「南京大虐殺まぼろし説」のような歴史修正主義とは距離を置き、相対的に穏当な記述に落ち着いたと評価できないこともない。
だが一方で、日本軍は規律正しい軍隊であるといった記述は残っており、矛盾を感じる。日本軍の軍紀の乱れは兵站の不足と並んで略奪・虐殺行為の主な要因である。そもそも規律正しい軍隊なら虐殺事件が起こるはずもない。文庫版は、虐殺行為の存在を事実上認めつつも、虐殺行為が発生した原因をごまかしているのである。
結局のところ、百田氏は表面的には妥協しつつも、内心では「光輝ある皇軍」を否定したくないのだろう。
また単行本では「『大東亜戦争は東南アジア諸国への侵略戦争だった』と言う人があるが、これは誤りである」と記し、「『大東亜共栄圏」という理想』のために戦ったと強調する。アジア・太平洋戦争は植民地解放戦争であると言いたいのだろう。
ところが文庫版では「正確な意味での侵略ではありません」と述べる。「正確な意味での侵略」という表現は難解だが、資源奪取など侵略的性格を(消極的に)認めているとも受け取れる。それでも「(侵略的な側面もあったが?)正確な意味での侵略ではない」と強弁するところに、太平洋戦争を何とか肯定したいという願望が見てとれる。
煩瑣になるのでこれ以上は列挙しないが、典型的な右翼の言説が散見された『日本国紀』単行本に比べると、文庫版は表面的には主張を薄めている。本質は変わっていないという批判はあろうが、たとえ表面的であったとしてもリベラルからの批判に対応し穏当な方向に記述を修正している点は、いわゆる「ネトウヨ本」とは一線を画す。
この〝柔軟性〟は百田氏の思想が穏健だからというより、『日本国紀』が「日本通史の決定版」として執筆されたというマーケティング上の事情によるものだろう。
同書は、いわゆる「ネトウヨ」のみを購買層として想定して出版された「ネトウヨ本」とは異なり、より広い層を狙っている。だからこそ極端な主張を排除した「穏健で中立的な歴史観」という装いが必要だった。実際、以下のコラムでも指摘したように、『日本国紀』は単行本段階から中立的な雰囲気を出すことに腐心している。文庫版はその路線をより明確にしたと言える。
その企みは奏功し、『日本国紀』は大ヒットした。むしろ私たちは、同書の表面的な穏当さに対してこそ警戒しなければならないのである。
なお本稿の内容は、2022年1月14日にゲンロンカフェで與那覇潤氏・辻田真佐憲氏と行った鼎談「歴史修正と実証主義──日本史学のねじれを解体する」での筆者の発言内容を基にしている。
同鼎談の要旨は以下の記事に掲載されているので、ご参照いただきたい。

【関連記事】
・通俗日本論の研究①:堺屋太一『峠から日本が見える』
・通俗日本論の研究②:渡部昇一『日本史から見た日本人 古代篇』
・通俗日本論の研究③:渡部昇一『日本史から見た日本人 鎌倉篇』
・通俗日本論の研究④:渡部昇一『日本史から見た日本人 昭和篇』
・通俗日本論の研究⑤:梅原猛『神々の流竄』
・通俗日本論の研究⑥:梅原猛『隠された十字架 法隆寺論』
・通俗日本論の研究⑦:梅原猛『水底の歌 柿本人麿論』
・通俗日本論の研究⑧:梅原猛『怨霊と縄文』『日本の深層』
・通俗日本論の研究(番外編):井沢元彦氏の反論に答える
・通俗日本論の研究⑨:井沢元彦『恨の法廷』
・通俗日本論の研究⑩:竹田恒泰『天皇の国史』