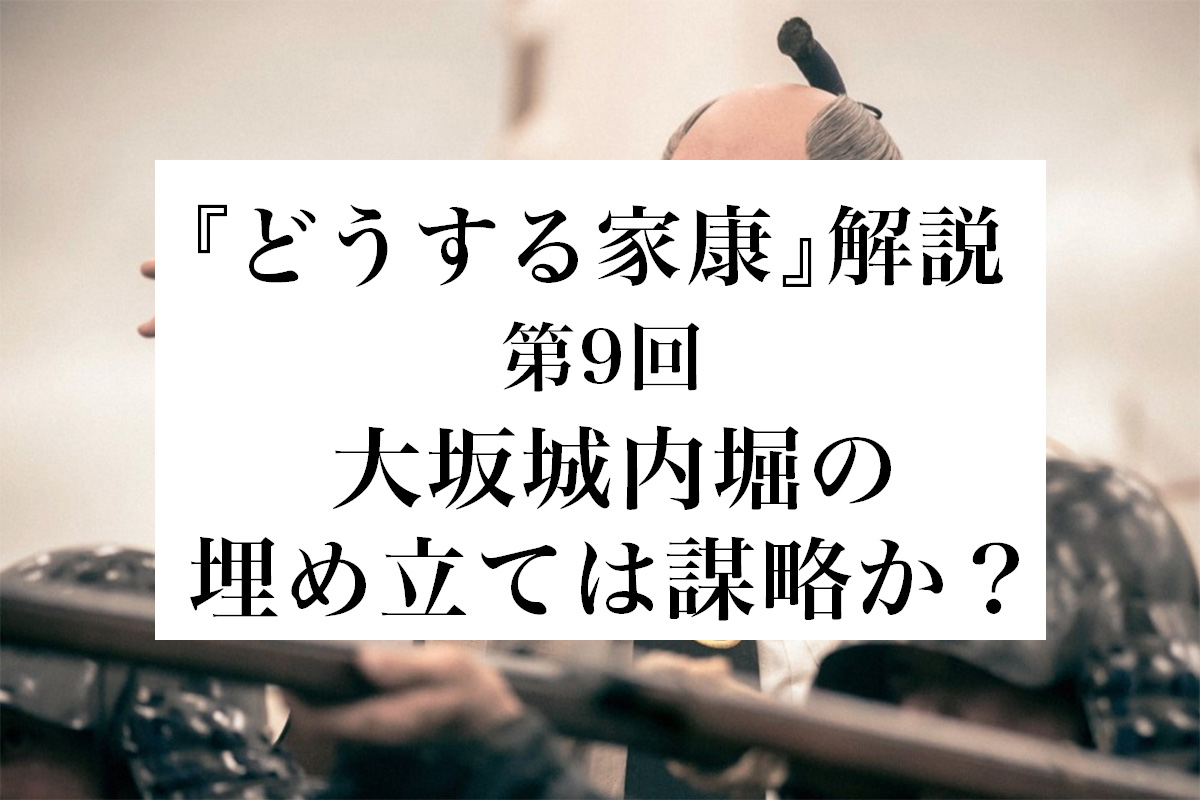先日、『どうする家康』が最終回を迎え、大坂の陣(慶長19年11月~慶長20年5月)が描かれた。劇中では、大坂城の内堀の埋め立てを徳川方が強行し、豊臣方が反発するという、おなじみの展開も見られた。

最終回「神の君へ」より
NHK「家康ギャラリー」
一般に、大坂の陣は徳川家康の悪名を高めたとされる。方広寺の鐘銘を口実に豊臣家を挑発して戦争に持ち込み、大坂城の内堀の埋め立てなどの謀略によって豊臣家を滅ぼしたという認識が「狸親父」イメージを決定づけた。
ところが江戸初期に成立した『大坂物語』『駿府記』は、冬の陣の和睦後、徳川方が二の丸の堀まで埋めたことを記すが、豊臣方の抗議に関する記述はない。
細川忠利・毛利輝元ら徳川方として従軍した諸大名は国元宛ての書状で、和睦条件に二の丸・三の丸の破却が入っていると述べている。これに従えば、本丸のみを残して他は全て破却することを、豊臣方も同意していたと見るべきだろう。
加えて、『本光国師日記』(金地院崇伝の日記)や『駿府記』を読む限り、大坂城の堀の埋め立て工事には約1ヶ月を要している。埋め立てが和議の内容に違反していたとしたら、豊臣方がその間、手をこまねいていたはずがない。
内堀埋め立てに豊臣方が同意するはずがない、と思う読者がいるかもしれない。しかしそれは、冬の陣で豊臣方が優勢だったという先入観に基づく誤解である。
大坂軍記などで豊臣方の奮戦が特筆されたため、冬の陣では豊臣方が勝ったように思われがちだが、事実は異なる。確かに真田丸の戦いなどで豊臣方は局地的な勝利を得ているが、攻城軍の中から寝返りが出なかった以上、戦略的には敗れたと言わざるを得ない。そもそも豊臣家は、豊臣恩顧の大名が味方してくれることに期待して挙兵したのに、誰一人馳せ参じなかったのである。
古来、籠城は外部から援軍が駆けつけてくれることを前提とした作戦であり、外に味方がいなければジリ貧になるだけである。『駿府記』によれば、豊臣方は木製の銃を大量に使用するほど武器の不足に悩まされていた。また『当代記』には、12月に入って城中の火薬が欠乏してきたことが記されている。武器・弾薬が底を尽きつつある中、大坂方は和睦に応じるしかなかった。大砲に怯えた淀殿が和睦を支持したという話は後世の創作にすぎない。
徳川方が騙して大坂城の内堀を埋めたという話は、いつ頃から語られるようになったのだろうか。家康・秀忠・家光3代に仕えた徳川譜代家臣の大久保彦左衛門が記した『三河物語』によれば、惣構(城の外郭)を崩すという条件で和睦したのに、徳川方は惣構の塀・矢倉を崩して外堀を埋めた後、二の丸の塀・矢倉も崩して内堀も埋めてしまった。豊臣方が抗議すると、徳川方は「惣構を崩すとは、本丸以外全て崩すということだ」と強弁したという。
この『三河物語』のエピソードは、江戸幕府の公式見解にも採り入れられた。貞享3年(1686)に成立した『武徳大成記』には以下のように記されている。豊臣方は「惣堀(惣構の堀、外堀)」を埋めるという条件で和睦するも、徳川方は二の丸・三の丸の堀(内堀)も埋めてしまう。大野治長(大蔵卿局の息子で豊臣方の総大将)が抗議するが、本多正純らに「惣堀とは全ての堀のことだ。二の丸・三の丸の堀を残そうとするのは再び籠城するためか」とはねつけられてしまった、と。
この話にはさらに尾ひれがついていく。肥前平戸藩主の松浦鎮信が編纂し、元禄9年(1696)頃に成立したとされる『武功雑記』は次のような逸話を載せる。豊臣秀吉の生前、伏見城が完成した時、徳川家康は「これほど堅固な城は、どう攻めても落とせないでしょう」と追従した。これに対し秀吉は「このような城は力攻めでは落ちない。いったん和睦して、和睦の証として堀を埋めて塀を破った上で再び攻めれば落とせる」と語った。家康は大坂の陣でこの策を用いたのだという。つまり、徳川家康が大坂冬の陣で講和したのは、豊臣家の存続を許すことにしたからではなく、大坂城を裸城にして攻めやすくするのが目的だった、というのである。
『武徳編年集成』も、生前の豊臣秀吉が大坂城攻略法として、いったん偽りの和議を結べば良い、と語っていたという逸話を紹介している。同書は「神君御調略的当して、一統の功業、ここに遂げんとす」と家康の策略を賞賛している。騙して内堀を埋めるのは卑怯、という認識は見られない。
これは、「徳川史観」においては、関ヶ原合戦の勝利によって徳川家康は天下人になった、と位置づけられていたからだろう。『三河物語』は以下のように語る。関ヶ原合戦後、豊臣秀頼に腹を切らせるべきという意見もあったのに、慈悲深い家康は秀頼の罪を許し、それどころか孫娘の千姫と結婚させた。ところが秀頼はその恩を忘れて謀反を起こした、と。こうした歴史認識は近世の諸書に散見され、江戸幕府の公式見解だったと思われる。
豊臣秀頼は謀反人だから、どんな手を使って討とうと卑怯ではない。むしろ実録『難波戦記』が語るように、力攻めではなく策略を用いるのは、味方の被害を最小限に留めるという点で賞賛されるべきことなのである。
だが近代に入り家康を神格化する必要がなくなると、家康の策略は一転して卑劣な謀略として非難されるようになった。ジャーナリストの徳富蘇峰は「大阪冬・夏の二陣は、家康が大阪を滅ぼすべき、腹黒き巧みより出来したるものと判断する者あるも、それを弁駁するに足る程の十分の資料はない」と家康を痛烈に批判している。
しかし、和睦交渉を細かく見ていくと、必ずしも豊臣家を滅ぼすための謀略とは言えない。慶長19年12月8日、豊臣方の織田有楽斎・大野治長が徳川家康に対し書状を送り、大坂城の牢人に寛大な処置を願うと共に、秀頼の国替えについて、どの国を想定しているのか内意を尋ねた(『駿府記』)。ここから、家康が和睦交渉において、当初、牢人の処罰・秀頼の国替えを条件として提示していたことが分かる。
家康は有楽斎らの問い合わせに対し、牢人を処罰しないことを約束すると共に、秀頼を大和国へ転封させるつもりだと伝えたという(『大坂御陣覚書』)。その後、家康は豊臣方に和睦条件として、淀殿を江戸に人質として差し出すか大坂城の堀埋め立てを要求した(『大坂冬陣記』)。
これに対して豊臣方は、淀殿を江戸に人質として差し出すが、牢人衆に恩賞を与えるために知行を加増して欲しいと要求した。家康は「牢人衆にどんな功があるというのか」と反発したため、交渉はいったん暗礁に乗り上げたが、豊臣方が加増の件を引っ込めたこともあり、和睦は成立した。
以上の経緯から分かるように、家康は甘言によって大坂方を騙すようなことはしていない。家康は徳川家の面子が保てる形の和睦を望んでいた。後で反故にするつもりなら大幅に譲歩して妥結すれば良いのにそうしなかったのは、和睦が成立した時には遵守する意思を持っていたからだろう。
12月20日に家康が秀頼に与えた誓詞では、牢人の罪は問わない、秀頼の身の安全と知行を保証する、淀殿を人質として江戸に差し出す必要はない、大坂城を秀頼が明け渡すならば望み次第の国を与える、といった条項が定められている(『大坂冬陣記』)。一方、秀頼も22日に家康に誓詞を提出し、今後は家康・秀忠に謀反の心を持たないこと、噂に惑わされず不審なことがあれば家康に直接問い合わせることを誓っている(『大坂冬陣記』)。
上の誓詞の内容だけを見ると、豊臣家にかなり有利な和睦と言えるが、土佐藩山内家に残る覚書では、大坂城惣堀を埋めること、牢人を召し放つことも秀頼側が約束したという。徳川家から見れば、豊臣家の今回の挙兵は「謀反」に他ならず、豊臣家が何も失わずに現状維持ということになれば、天下を治める徳川家の威信に関わる。実際、『大坂御陣覚書』によれば、和平会談で家康側は「大御所様(家康)自ら出馬して、何も得ずに和睦しては、武門の名誉に傷がつく」と主張している。また、反乱の再発防止のためにも、大坂城の無力化と牢人衆の追放は必須だった。
これらを踏まえると、和睦内容のうち、直ちに履行すべき事項は、徳川家による秀頼の地位確認と牢人の赦免、徳川方・豊臣方双方による大坂城の堀の埋め立てであったと言えよう。秀頼の転封や秀頼あるいは淀殿の江戸在住を家康が強制しなかったのは、豊臣家の面目への配慮であり、最終的には豊臣家に受け入れさせようと考えていたと推測される。
豊臣家の武力では、牢人衆の追放という条項を履行するのは困難である。となると、代わりに秀頼の転封、もしくは秀頼・淀殿いずれかの在江戸を受け入れるほかなくなる。この条件が実現すれば、豊臣家が家康に臣従したことが明確になる。もともと大坂の陣は、豊臣家を臣従させるために家康が起こした戦争である。逆に言えば、豊臣家が臣下の礼をとりさえすれば、豊臣家を無理に滅ぼす必要は家康にはなかったのである。
【関連記事】
・大河ドラマ『どうする家康』解説①:桶狭間合戦の実像
・大河ドラマ『どうする家康』解説②:武田信玄は上洛を目指していたか
・大河ドラマ『どうする家康』解説③:鉄砲3段撃ちはあったか(前篇)
・大河ドラマ『どうする家康』解説④:鉄砲3段撃ちはあったか(後篇)
・大河ドラマ『どうする家康』解説⑤:小牧・長久手合戦の実像
・大河ドラマ『どうする家康』解説⑥:家康はいつ秀吉に臣従したか
・大河ドラマ『どうする家康』解説⑦:七将襲撃事件は「訴訟」だった?
・大河ドラマ『どうする家康』解説⑧:小早川秀秋は事前に裏切っていたか?