アゴラでは日々多くの記事を配信しており、忙しい方にはすべてを追うのは難しいかもしれません。そこで、今週の特に話題となった記事や、注目された記事を厳選してご紹介します。
政治や社会保障を中心に、国際情勢やビジネス、文化に至るまで多岐にわたる内容を網羅。各記事のハイライトを通じて、最新のトピックを一緒に深掘りしましょう!
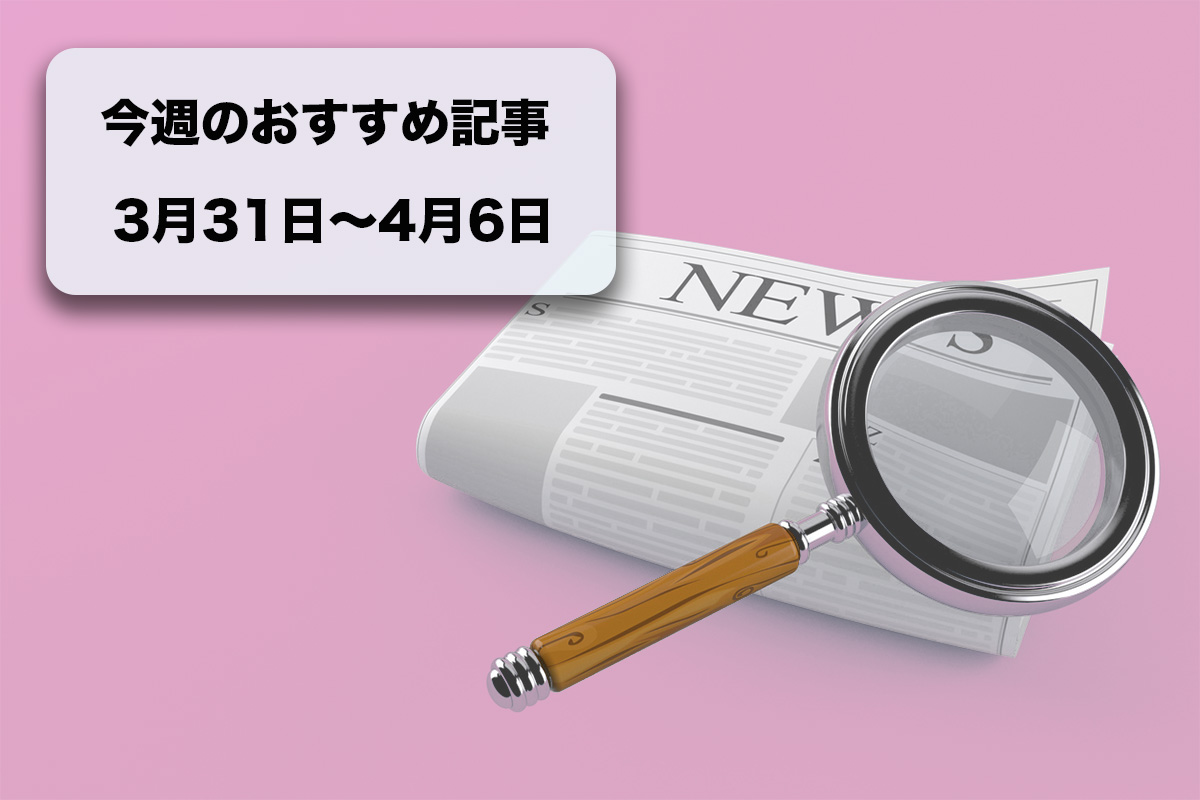
政治・経済
立憲民主党は蓮舫氏の参院選比例代表への公認内定を見送りました。高い知名度を持つ一方で、労組系候補の落選リスクや過去の選挙活動への不満が背景にあります。党内では賛否が分かれ、蓮舫氏の国政復帰に慎重な姿勢が見られます。比例代表制度の特性も判断に影響しています。
立憲民主党が蓮舫氏の参院選公認内定を見送りの因果応報(アゴラ編集部)

■
中野サンプラザ再開発計画は、事業費が突如900億円超も増額され、議会や住民の反発を受けて白紙撤回となりました。再整備は議会の議決対象となり、今後の再計画では中野区民の声を反映した慎重な議論が必要とされています。財政面では借金返済や固定資産税対策も進められています。
サンプラザ再開発計画白紙へ:中野区議会からみた顛末(加藤 拓磨)

■
選択的夫婦別姓は個人の自由を尊重する制度ですが、保守派は「家族の一体感の崩壊」として反対しています。これは明治時代の「家制度」や男尊女卑の価値観に根ざしており、同姓を強制する現行制度は国際的なジェンダー平等の流れとも乖離していると筆者は指摘します。
選択的夫婦別姓反対は明治の「家制度」を守るイデオロギー(池田 信夫)

■
石破首相が国会で「食料品の消費税ゼロ」を一概に否定しないと発言し、波紋を広げています。これに対し国民民主党の玉木代表は「全品目5%減税」を主張しましたが、13兆円の税収減やインフレ加速の懸念も指摘されています。選挙を見据えたパフォーマンスとの見方もあります。
消費税を5%に減税? 石破首相の発言に玉木代表が反応(アゴラ編集部)

■
筆者は、トランプ元大統領の政策や手法に否定的ながらも、彼のリーダーシップはポピュリズムではなく、自己の信念を愚直に貫く「始動者」としての姿勢にあると評価します。迎合ではなく、批判を受けながらも時代を切り拓こうとする姿勢に、日本のリーダーも学ぶべきだと提言しています。
トランプ現象はポピュリズムではない:時代を切り拓くリーダーシップの重要性(朝比奈 一郎)

■
トランプ大統領は、日本に24%の追加関税を課す「相互関税」政策を発表しました。これにより輸入車にも25%の関税が適用され、日本経済に深刻な影響が懸念されています。保護主義的政策は1930年代の世界恐慌や戦争の教訓を想起させ、国際的な自由貿易体制への打撃が懸念されています。
トランプ関税、日本に24%の衝撃:世界大戦を招いた保護主義の再来か(アゴラ編集部)

■
トランプ氏が発表した「相互関税」は、日本に24%、中国に34%など高率で、世界経済に深刻な混乱を招くと指摘されています。不確実性が企業投資を停滞させ、需要減退と不況を招く可能性が高く、最終的に米国自身も損失を被るとIMF元理事ブランシャール氏の分析をもとに警鐘が鳴らされています。
トランプ関税は「不確実性」で世界経済を大混乱に陥れる(池田 信夫)

■
トランプ氏の「相互関税」発表により、米景気の不透明感が強まりドルが急落、一時1ドル=145円台前半まで円高が進行しました。市場では円が安全資産として買われ、FRBの利下げ観測もドル安を後押ししています。ただし、長期的には貿易赤字縮小などで再びドル高に転じる可能性も指摘されています。
ドル円が急激に下落し146円割れも長期的にはドル高に転じるか?(アゴラ編集部)

■
トランプ氏の「相互関税」政策は、合理性を欠く一方的な措置で、米国労働者の不満を背景にした政治的対応です。グローバル化による格差拡大や雇用喪失への反発が背景にあり、保護主義の再来が懸念されています。筆者は、日本がTPPを通じて自由貿易のリーダーとなる好機と見るべきだと提言しています。
トランプ関税の背景にある「グローバリゼーションの逆説」(池田 信夫)

■
今月の言論アリーナです。
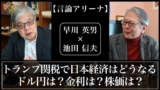
国際・エネルギー
尹錫悦大統領の弾劾と、反日姿勢の強い李在民氏の台頭により、日韓関係の悪化が懸念されています。筆者は、真実に基づいた中立的な韓国史の必要性を訴え、自著『誤解だらけの韓国史の真実』改訂版を紹介。近年の遺伝学や言語学の成果も踏まえ、感情論でなく冷静な歴史認識の重要性を強調しています。
李在民韓国の反日化が予想される中で『韓国通史』を知る(八幡 和郎)

■
米ペンシルベニア州の補選で民主党が、トランプ氏が大差で勝利した選挙区を逆転し、共和党に大打撃を与えました。共和党は下院の多数派を維持できない可能性があり、政権への不信が背景にあります。今後の補選次第で政局は大きく揺れ動く見通しです。
民主党、州議会補選で大金星: 共和党が米国下院で少数派に?(アゴラ編集部)

■
プーチン大統領が提案した「ウクライナの国連暫定統治」構想は、停戦交渉を巡る駆け引きの一環であり、トランプ氏も強く反応しました。ロシア・ウクライナ・アメリカの首脳がSNS等で発信する「劇場型」交渉が続く中、日本は冷静に事態を見極める姿勢が求められています。

■
ドイツのメルツCDU党首はSPDとの連立交渉で財政政策を大きく転換し、党内からの反発を招いています。保守的財政規律を訴えてきたにもかかわらず、巨額の赤字財政容認に転じたことで「公約違反」との批判が高まり、党員離脱も発生。一方、AfDは支持を伸ばし、CDUを追い越す可能性が出てきています。
CDU党内で求心力を失うメルツ党首:更に飛躍するAfD(長谷川 良)

■
トランプ氏の「相互関税」政策は一方的で市場混乱を招き、特に日本に24%課税するなど根拠の曖昧さが問題視されています。筆者は、米国依存からの脱却と自立的な国際戦略の構築が日本に必要だと強調。今こそ官民一体で新たな方向性を模索すべきだと訴えています。
正気ではないトランプ氏の行動:日本はアメリカに頼り過ぎた点を反省すべし(岡本 裕明)

■
トランプ大統領の高率関税政策は、経済合理性よりも19世紀モンロー主義や保守思想に根ざした政治的判断です。世界恐慌や大戦の教訓として自由貿易が重視されてきた中、米国の国益を最優先する姿勢は、時代の転換点を示しています。日本もその背景を正確に理解し、備えるべきと筆者は訴えます。
「トランプ関税」の政治思想は経済学の教科書には書かれていない(篠田 英朗)

■
韓国憲法裁判所は尹錫悦大統領の弾劾を妥当と判断し、即日罷免が決定されました。非常戒厳発動や軍の国会突入などが争点で、現職大統領の逮捕・起訴は史上初。今後60日以内に大統領選が行われる見通しで、反日姿勢が強い李在明氏の政権誕生が現実味を帯びています。
韓国憲法裁が尹大統領の罷免を決定:超反日政権の誕生は秒読みに(アゴラ編集部)

■
トランプ政権は国内エネルギー生産拡大と規制緩和を強化し、高評価を得る一方で、温暖化対策軽視や「トランプ関税」への批判も強まっています。再生エネ支援の削減や国際枠組みからの離脱方針は不透明感を招き、エネルギー政策全体に不確実性が残る中で、経済・環境両面の影響が注視されています。

■
気候モデルは地球の過去の湿度すら正確に再現できず、特に乾燥地域の比湿・相対湿度と観測値に大きな乖離があります。将来の大雨や山火事の予測に用いるには不十分であり、筆者は「将来予測の前に過去の検証を行うべき」と警鐘を鳴らしています。モデルへの過信に注意が必要です。
湿度も再現できない気候モデルで大雨も山火事も予測できる筈がない(杉山 大志)

■
再エネの不安定さを火力や原子力で補う「バックアップ電源」という言説は、設備の設計原理を無視した誤解に基づくものです。これらの発電は頻繁な起動・停止に適さず、効率低下や寿命短縮のリスクが伴います。現実的なエネルギーミックスには、各電源の特性を理解した上での設計と議論が必要です。
「バックアップ電源」という誤解が生む「再エネの主力電源化」(室中 善博)

■
IEAのエネルギー予測シナリオ「STEPS」は、太陽光発電の導入量や中国の電化率・CO₂排出削減見通しが年々楽観的にシフトしており、現実の政策目標や技術的制約と乖離しています。特に中国の太陽光発電設備利用率の上昇には根拠がなく、筆者は「根拠ある予測」の必要性を強く訴えています。
国際エネルギー機関IEAの不可解な中国シナリオ(中山 寿美枝)

ビジネス・IT・メディア
40代は人生の折り返し地点であり、筆者は「ズレた承認欲求」「他者比較」「無駄なプライド」の3つを手放すべきと説きます。社会貢献による健全な自己肯定、比較に縛られない幸福追求、変化を受け入れる柔軟さを持つことで、より良い人生と仕事の成果が得られると述べています。

■
日本の就職制度は安定的である一方、新入社員の扱いは時代とともに大きく変化しています。企業は若者の離職を防ぐため、希望配属の尊重や丁寧な対応を行い、「腫れ物に触る」ような姿勢が主流に。若者側も批判的・知識先行型の傾向が強く、会社側はチームワークの難しさと向き合っています。
大きく変わった新入社員への扱い:会社側は腫れ物に触る感覚(岡本 裕明)

■
任天堂はNintendo Switch 2を正式発表し、ゲームチャット機能やマウス操作可能な新型Joy-Conを搭載。これにより、モバイル性と操作性を両立し、ゲーミングノートPC市場をも侵食する破壊的イノベーションとなっています。ただし、5万円近い価格は家庭の負担となる可能性もあり、子どもの体験格差が懸念されています。
進化するSwitchが次に食い荒らすのは何処か(金尾 泰之)

■
「識学」は誤解や錯覚を排し、役割に集中できる組織づくりを目指す理論です。安藤広大氏は「過度に部下を褒めると期待基準が下がり、組織全体の実力低下を招く」と指摘。褒める際は成果が基準を大幅に超えた時に限定すべきとし、信頼関係と適切な評価の重要性を強調しています。

■
フジテレビに関する第三者委員会の報告書で、女性社員へのセクハラ・性暴力、被害の隠蔽、加害者擁護、コンプライアンス軽視など深刻な実態が明らかになりました。被害者は異動され、加害者は処分されず、組織ぐるみの体質が批判されています。報告書はフジテレビの構造的問題を厳しく指摘しています。

■
大阪・庄内のマクドナルド店舗が「異常に美味しい」とSNSで話題となり、その背景には現場スタッフの丁寧な仕事ぶりがあると筆者は指摘します。この現象は日本の「現場力」の強さと、それを支える労働環境の限界を示しており、今後の日本社会が「高品質な現場文化」をどう維持していくかの分岐点にあると論じられています。
噂の大当たり店舗『マクドナルド庄内店』が突きつける”日本社会の分岐点”(倉本 圭造)

■
ピラミッド型組織の問題は構造自体ではなく、責任の範囲が曖昧な運用にあると識学の安藤広大氏は指摘します。情報の非対称性や粘着性が組織慣性を生み、変革を阻害。適切なマネジメントによって、ピラミッド型は最も効率的な成長を実現できると論じられています。

科学・文化・社会・一般
自身の記事への古谷経衡氏の法的脅迫に対し、具体的な反論がないままスラップ訴訟をほのめかす古谷氏の態度を批判。署名偽造の事実検証を避け、名誉毀損に当たる発言まで行っていると指摘します。言論には言論で応じるべきだと訴え、必要なら反訴も辞さない構えを示しています。
批判に脅迫で応じた「リベラル論客」・古谷経衡氏に告ぐ(與那覇 潤)

■
佐賀県伊万里市の松浦鉄道・浦ノ崎駅は、満開の桜に包まれる春の名所として知られ、駅周辺では「桜の駅まつり」が開催され多くの人で賑わいました。昭和初期に植えられた桜が美しく咲き誇り、鉄道と自然の調和が人々を魅了。静かに楽しみたい人には久原駅もおすすめです。

■
大阪城は豊臣秀吉、徳川秀忠、そして昭和期と3度にわたって天守閣が築かれました。現在の天守閣は昭和に建てられた鉄筋コンクリート製で、豊臣時代の意匠と徳川時代の漆喰を融合したデザインです。近年オープンした「豊臣石垣館」では、埋もれていた豊臣時代の石垣を展示し、歴史的経緯や城の構造が学べます。
豊臣時代・江戸時代・現在の大坂城天守閣を比較する(八幡 和郎)

■
年配者がくどく長話をしがちなのは、①話の引き出しが多い、②話し相手が少なく飢えている、③聞き手の反応に不安があるためと筆者は分析します。改善には「復唱で共感を示す」「遮らない」「短く話す」などの工夫が有効で、年齢を重ねたら改めて話し方を学ぶ姿勢が大切だと説かれています。
おじさん、おばさんがくどい長話をやりがちな理由(黒坂 岳央)

■
福岡の桜の名所である舞鶴公園と西公園を訪れました。歴史ある福岡城跡に咲く満開の桜と、海を望む西公園の桜は、それぞれ異なる魅力を持ち、春の風景を堪能できます。公園では屋台も楽しめ、飛行機や海の景色との共演も見どころです。














